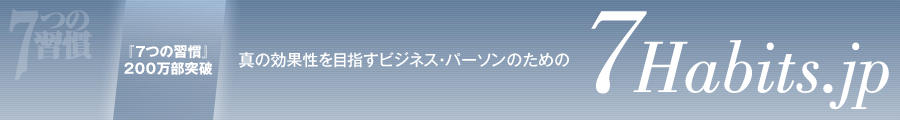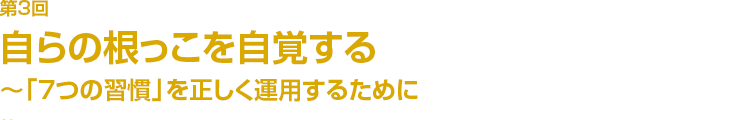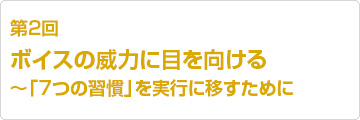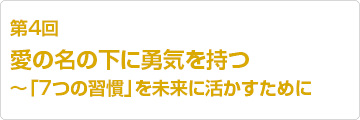●グローバリズムと人格主義の関係
- 竹村
- 今のような激流の時代になればなるほど、自分自身の軸というものをきっちりと持っていないと、本当の意味でうまく時間を使ったり、行きたい方向にちゃんと進むということが難しくなるような気がします。
- 安藤
- 時代の変化以上に移ろいやすいのが個人の感情だと思うんです。昨日は好きだったものが、今日はもう嫌いになったり興味を持てなかったり。そういう移ろいやすさを抱えている個人が、変化する時代といううねりの中で、それでも強く信じるもの、変わらないものを持ち続けるのって、すごく困難なことだと思うのですが。
- 竹村
- そこはまさにそうですね。私どもの企業研修で、最もリクエストが多いテーマというと、やはりグローバルになるのですが、何をもってグローバルとするのか、そこの定義ってイマイチ曖昧ですよね(笑)。まあ、一般的には語学だったり異文化だったりするのかもしれませんが、私どもが研修を請け負う際には、人格主義と個性主義、別の言葉でいうとマインドとスキル、それをグローバルというテーマの中でお伝えしていくことにしています。

どういうことかといいますと、個人としての自己をしっかり持ちつつ、他の人たちと共存しながら、その人たちに影響を与え、巻き込んでうまくやっていく。それこそが、本当の意味でのグローバルマインドであり、グローバルリーダーとしての資質になるということなんです。 - 安藤
- 『7つの習慣』の中にも、これに近い話が出てきましたよね。
- 竹村
- ええ、『7つの習慣』でいうと、Win-Winの条件、「勇気と思いやりのバランス」になります。自分自身の軸をちゃんと持って、それを外に向けて主張していく。他の人にきちんと理解させ、相手のこともちゃんと理解して、双方が互いを受け入れてやっていく。この両方が備わって初めてWin-Winが可能になり、またグローバルといえるわけです。
先ほど、安藤さんがおっしゃったように、確かに困難なことではありますが、そういう両面の能力が個人に求められる時代になってきていると思います。
●コンテンツを伝えるためには「根っこ」がいる
- 安藤
- スキルに依拠した個性主義というのは比較的わかりやすいですよね。でも、今ここに来て、人格主義というものの大事さに私も気づきつつあるという気がします。
慶應義塾大学の在学中、1年間の交換派遣留学に行かせてもらったことがあったんですが、向こうでは思ったよりも自分を主張することができなくて、今思えば、そういう経験ができたのでよかったのですが、留学そのものは大失敗に終わりました。
留学で本当に大事なのは、スキルとしての語学を磨くことよりも、目の前の外国人と何かを通わせることだったのに、当時の私には何も伝えるべきもの、シェアしたいテーマがなかった。好きだった三島由紀夫にしろ、アガサ・クリスティにしろ、それを持ち出したところで、彼らにいったい何を語りたいのか、そういう意味でのテーマが私の中になかったのです。
反対に、最初はどんなに下手でも急激に語学力を伸ばしていく人って、自分の国のことを知ってほしいとか、これだけ何かに夢中になっている気持ちをシェアしたいとか、とにかく相手と何か心を通わせたいという強い思いやテーマを持っていました。
その経験があるせいか、そういうテーマなしに、語学を磨くとかコミュニケーションスキルを磨くとか聞くと、どうもピンとこないのです。 - 竹村
- 語学やスキルを根っこなしで学んだとして、じゃあ、そこのコンテンツはどうするの? という話ですものね。
- 安藤
- 本当にそうなんです。
●人格主義の国、日本
- 竹村
- 人格の重要性に目を向けることなしに、成功や幸福を追求しても、本当の意味で手に入れることは難しいだろうと思います。
- 安藤
- そういえば、『7つの習慣』において、人格主義の回復ということを改めて打ち出されるようになりましたが、それはどういう理由からですか。
- 竹村
- 実は、そこに新しく完訳版をつくった理由の一つがあるんです。旧版には「成功には原則があった!」という副題がついていましたが、あれは日本のマーケティング戦略用に考えたもので、原書の本当の副題は「人格主義の回復」だったんですよ。
- 安藤
- そうだったんですね。最初の副題もわかりやすかったですけど。
- 竹村
- ええ、それで100万部も売れたんです(笑)。演出の仕方としては大成功でしたし、よかったと思いますが、「7つの習慣をやれば私も成功できる!」という雰囲気が独り歩きしてしまって、本来の意図とは少しずれているかなと。そこに、リーマンショックがあって、東日本大震災が起きて、日本中が痛みと苦しみにあえぐ中で、人格主義の回復というのはタイミングとして合っている気がしました。今こそ日本人が本来持っている価値観や精神性に回帰していくべきタイミングなのではないかと思いました。
- 安藤
- 日本にはもともと人格主義があったと?
- 竹村
- というか、日本は元来、それでずっとやってきた国だと思うんです。むしろ、長い日本の歴史の中で見たら、今のいわゆる個性主義的な、勝ち組とか負け組とか、そういった価値観のほうが異質ではないでしょうか。“Be good”、よりよい人になったり、よりよい人生を送ったりするために必要なものを、日本人はもともと持っていたのに、戦後の西洋化によって手放してしまった気がします。経済的にも精神的にも教育面でも、家庭ですらおかしくなってしまって、今はあらゆる側面で病んでいるのかもしれません。
この問題の根本、すなわち人格的なところにメスを入れないかぎり、本質的な、長期的な結果って変わっていかないんじゃないかと危惧しています。
●良心と自覚が“Be good”の正しい運用を促す
- 安藤
- 本当に今って、バランスを欠いていますね。たとえば、仕事がないという人がいる一方で、過労死寸前まで働く人たちがいて。すごく悩ましい状況です。
- 竹村
- そう、ギャップがあって、すごく極端です。古きよき日本では、公的成功に対する感覚が自然な形で根づいていて、皆に分け与え、皆で分け合うというのが当たり前でした。殿様のような支配者、特権階級はごく一部で、庶民には庶民の生き方、共有の知恵があった。それなのに、戦後、民主主義が発達していく中で、どんどんアメリカナイズが進み、どんどんどんどん格差が広がってしまった。
- 安藤
- 私は「森羅万象」という言葉がすごく好きで。生きとし生けるものすべてに神とか魂が宿っているという捉え方、こういう日本的な感性って素晴らしいと思うんです。

パズルのピースって、一つひとつ形が違っていて、それぞれに突起や凹みがあるからこそ、他のピースとハマることができるわけで。人間も個々の尖ったり凹んだりしている部分こそがすごく大切で、それがあるから他の人を救ったり、何かの役に立ったりできる。だから、生きとし生けるもの皆に価値があると、すごく感じるんですよね。 - 竹村
- なるほどね。『7つの習慣」について、ときどき言われるのが、こういうものを学ぶと、みんな金太郎飴みたいに同じような人間になっちゃうんじゃないかと。でも、決してそんなことはないんです。学んでいくプロセスは同じかもしれないけど、中のコンテンツは一人ひとり違うわけですから。
コヴィー博士のいう“Be good”って、「よりよい人になっていきましょう」というよりも、むしろ「本来、あなたがあるべき人物になっていきましょう」というほうが、より正確に彼の思いを伝えられるような気がします。それが『7つの習慣』において、コヴィー博士が最も伝えたいところなのかもしれません。 - 安藤
- まさに、ボイスにつながるところですね。
- 竹村
- そうなんです。コヴィー博士は「良心」という言葉がとても好きで、同じようによく用いるのが「原則」という言葉です。『7つの習慣』の中で、原則とは、古今東西、時代や文化の違いによって影響を受けることのない自明の理であり、個々の価値観の外側にあるものだと定義しているんですが、これが『第8の習慣』になると、原則とは究極的には、私たちの良心に属しているものだ、という表現になっているんですね。たとえば、身勝手に振る舞ってしまったとき、「自分には親切さがない」と思うこと自体、その人の心の中にその感覚があるからこそ、感じるわけですから。
- 安藤
- 言われてみたら、そうですね。
- 竹村
- だから、それを持っている人ならば、それをちゃんと運用できるはず。だから、皆でそういう人になっていきましょう、そのために役立つツールとして、「7つの習慣」を使ってほしいということなんです。