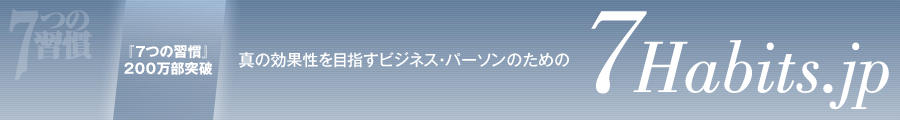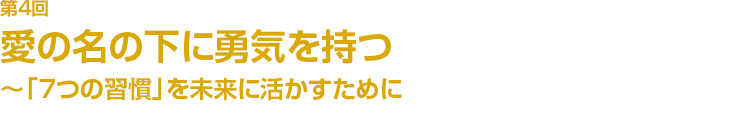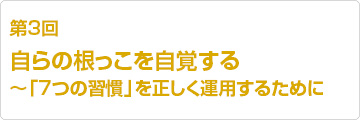●恐れという感情の源には愛不足がある
- 安藤
- 人って本来、困った人を助けられたら自分にも喜びが返ってくるし、頼られたら嬉しいという気持ちがあると思うんです。でも、ありのままの自分でいることが怖い。やっぱり余裕がないのでしょうか。本当の自分に戻ること、ありのままの自分でいることをいちばん阻むのは、「恐れ」という感情なのかなと。
もしかすると、恐れという感情って、すべてにおいて、ものすごく深く根を張るものなのかもしれませんね。人から嫌われることが怖い、本当に思っていることを言うのが怖い、仕事で必要なことなのに意見するのが怖い。恋人同士であっても夫婦であっても、相手に自分のありのままを伝えて向き合うことが怖い。このようなすべての根幹にある恐れを乗り越えるために、「7つの習慣」をどう活用できるのか、とても興味があります。
- 竹村
- 「7つの習慣」の中で、恐れを克服するのに役立つものというと、たぶん第1の習慣になるでしょうね。外界からの刺激やストレスがあったら、まず自分の心にスペースを設けて、その余白の中で自覚や良心を稼働させ、適切な選択を行います。そうすることで、マイナスの感情やネガティブな反応を克服することができるという内容です。
「7つの習慣」では、この「自分が何を選択するか」という部分を重視していますが、もしコヴィー博士が今ここにいたら、たぶん違うことを言うような気がします。 - 安藤
- どういうことでしょう。
- 竹村
- 他者とのかかわり、他者からの刺激に対し、なぜ恐れを感じるのかと問うたら、「それは、あなたの中に愛が足りないからだ」と、コヴィー博士は答えるでしょう。
会社の同僚に対しても、世の中に対しても、見知らぬ人に対しても、愛というものを持つことが、より大きく深く、自分たちの心を豊かにするものだということは、誰も否定はしないと思います。であるならば、他者の存在をどうして恐れる必要があるでしょう。自分の中に愛が足りないから、他者を恐れる感情が生まれてしまうのです。 - 安藤
- それは、相手に対する愛であり、自分に対する愛でもあるということですね。
- 竹村
- そうですね。だから、恐れる気持ちがあるのなら、逆に「インサイド・アウトで、あなたから愛しなさい」と、コヴィー博士は言われるのではないでしょうか。
- 安藤
- 素晴らしい、感動的な答えですね。すごく共感します、その答えに。
●恐れを手放すと自分自身の可能性が広がる
- 竹村
- たとえば、親って子どもの命が危険にさらされたら、自分の命の危機なんて顧みないですよね。でも、同じように危険な状況でも、意識が自分自身に向いているとき、自己の領域内に留まっているときは、やはり恐怖を感じるだろうと思うんです。人って、それをやることが自分のためではなくて、社会のためだったり、周りの大事な人たちのためだと思うと、勇気や力が湧く生き物で、そこはやはり愛だと思うのです。それが情熱という形になるとき、自分の中にある恐れを克服することができる。逆に言えば、そういう思いがない限りは、何をどうやってもダメだと思うのです。

- 安藤
- 日頃、「やりたいこと、好きなことがあるのに、それを口に出して表現できない、実行に移すことができない」という相談を寄せられることがとても多い。私自身も長い間そうだったのですが、その経験から、「どうしても成し遂げたいことのために、情熱が恐怖を圧倒する瞬間」というのがあるような気がしてならないのです。
とても怖い、恐ろしくてたまらない。それでも私はここに行きたい、これをやりたい。そこまで思う情熱って、愛と言い換えることもできるような気がします。それと、時間にも直線方向だけじゃなくて、濃度や深度のようなものがあると思う。だから、思いきり濃く深く生きるというのも一つのやり方ではないでしょうか。恐れを克服するカギは、そのあたりにあるような気がします。 - 竹村
- コヴィー博士は、『7つの習慣』を世に出すために、大学の先生を辞めて、私財を投げ打って会社をつくったんですよ。すでに年齢を重ねていましたし、リスクも決して小さくないですから、それなりの恐れはあったはずです。もし彼が、「将来、上場して、ビジネスチャンスを広げて」みたいなことを考えていたら、たぶんものすごく怖かったでしょうね。でも、コヴィー博士の意図は、自分の考えを世の中に広めて貢献したいということだけでした。人間に対する愛情だったり、自分自身のボイスに押しやられたり、そういう純度の高い情熱しかなかったから、必要以上の恐れを感じずに、実行に移せたのではないかなと思うんですよ。
- 安藤
- 恐れを手放すことができると、自分の可能性が広がるんですね。
- 竹村
- コヴィー博士は非常に楽観的な人なんですよ。どんなことがあっても、恐れるということが全然なくて。エレベーターの中で見ず知らずの女性にも握手を求めて、“You are beautiful”って言ってしまうような(笑)。本当に愛情深い人でした。人間、そこまでいけると、何も恐れずにいられるようですね。
- 安藤
- 恐れのメガネをかけると、目の前の現実が歪んで見えますものね。きっとコヴィー博士は、ありのままを見ようとするメガネを磨き続けた方なのでしょう。
●これからの世界に対して日本ができること
- 竹村
- これから先の世界について、少しお話ししましょうか。たとえば、地球がどのようになっていくのか、ある説では、食料や地下資源以前に、水が足りなくなるということらしいです。おそらく2030年くらいに。
- 安藤
- これだけ海があっても?
- 竹村
- ええ、水を巡って戦争が起こるような時代が来るかもしれません。そこでまず、先進国に住む人たちは、いわゆる第三国の人々に対して、今後どういう道を進んでいくべきか、グローバルと歴史の視点をもってしっかり考え、示していかなければならない。私の勝手な思いですが、そこを先導していくことができる国は、日本しかないのではないかと思うのです。未曽有の震災があっても暴動が起こるわけでもなく、皆が協力し合える国は本当に珍しいと思います。
- 安藤
- 自然に、譲り合いができたり、おすそ分けができたりします。
- 竹村
- それが日本という国なわけですから、これから世界がどうあるべきなのかを示していく責任が、私たちにはあると思うんです。だからこそ、人格主義的なもの、日本人が本来持っている長所なり美点を復活させていく必要があって、それが日本のためにも世界のためにもなると思います。
- 安藤
- 先日、インドネシアのジャカルタに行ったんですが、大変な建設ラッシュでした。あちらの知人によれば、今後20年でフィリピンのマニラを抜くだろうと見られていて、世界一の成長率を誇る都市だと言われているそうです。その反面、実際にはまだまだ追いついていないところがある。インドネシアの富裕層はわずか8%ほどで、それ以外の人たちは、自分の人生について、キャリアプランやライフプランを立てることもなく、せっかく立ち退きなどでまとまったお金を手にしても、皆すぐに使ってしまうそうなんです。

そういう状況を見ると、日本人が、これからの国、今伸びている国やそれを待ち望んでいる国に対して提供できることって、本当にたくさんあると感じました。よくいわれるホスピタリティなどもそうですが、人生というものをもっと大局的に捉えて、よりよく生きるために、自分は今、何をすればいいのか。現在のことだけでなく、3年後、10年後を考える視点が必要だと思います。自分の人生には意味がある、その長い時間を生きてきただけの価値があるということを、一人ひとりの人が自覚するためにも、すごく大事な視点だと思います。 - 竹村
- おっしゃる通りですね。
- 安藤
- こんなふうに考えられるようになったのには、やはり『7つの習慣」からの影響が大きいと思います。決して小手先のスキルではなくて、さらっと書いてあるような項目であっても、常に自分自身の鍛錬とか意識づけを促される。意識を向ける方向を変えて、従来の認知の仕方をガラッと変えて、そして行動も変える。いい意味で、一生のテーマだと思うんですよ。「全く違う自分に生まれ変わりましょう!」 といった軽いものではなくて、自分自身ととことん向き合うことで、自分が大きく変わっていく。たぶん、いつどこで出会っても、その人の残りの生涯の中で、大きな影響を与えてくれるものだと思います。
- 竹村
- 素敵なお言葉ですね。ありがとうございます。
- 安藤
- とても楽しかったです。ありがとうございました。