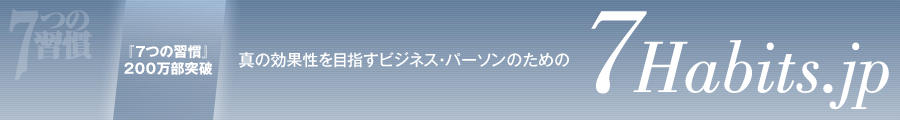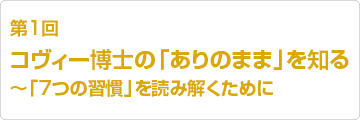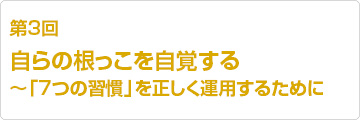●ボイスを無視して生きることはできない
- 安藤
- 今、週3回ほど大学で講義をしているんですが、今朝の授業で「自分の心に従って決断をしてください」という話をちょうどしてきたところなんです。彼らがこれから社会人としてどう生きるかという前に。私自身、常に自分に言い聞かせている言葉なのですが、今こそ、ボイスという言葉がすごく響くような気がしています。
- 竹村
- 確かに、そういう気がします。
- 安藤
- 最初に出した『冒険に出よう』という本の中でも、繰り返しボイス的なことを書いています。自分で主体的に考えるとか、自分の頭で考えて動くとか、感じたままにやってみるとか。私がそういうことをたびたび書くのは、自分が長い間、そうできなかったことの裏返しなんです。絵を描くことや文章を書くことがすごく好きだったのに、偏差値的な教育とか受験に呑まれて、いつの間にか好きなことを忘れてしまった。それで入った大学は第一志望ではなくて、就職先も本当は出版社ではなく、別の業界に行きたかったんです。

- 竹村
- それで、集英社でご活躍されていたにもかかわらず、若くして起業されたのですね。
- 安藤
- 周りの人たちからの期待とか、いろいろな欲に寄り道している間に、自分のやりたいことや心が見えなくなっていました。30歳を前に、そういう生き方が本当にいやになって会社を辞めたんです。自分のボイスに従って生きないと、あとで後悔する。それだけはいやだって。ただ、自分のボイスってとても小さい声なんですよね。だから、他の声の大きさにかき消されてしまいがちです。
- 竹村
- 日本人の国民性とか受験社会ですと、特にそうなりやすいかもしれませんね。
- 安藤
- でも、『7つの習慣』が、日本だけではなくて世界中で読まれているということは、主体的に生きたいとか、本当にやりたいことしたいっていう渇望が、世界中の人たちにあるということなのかなと。
- 竹村
- それは本当にそうだと思います。古今東西、老若男女に通じる原則だからこそ、『7つの習慣』は長い間、世界中で読み継がれているのです。
●公的成功と私的成功に対する東西の感受性
- 安藤
- 『7つの習慣』の中にある習慣のうち、日本と諸外国では、響き方が異なる習慣ってありますか。そこに国民性の違いが見えたら面白いなって。
- 竹村
- その視点は興味深いですね(笑)。フランクリン・コヴィー社は40拠点、120か国で展開していますが、そういうアンケートはとったことがないんですよ。ただ、本社が米国なので、向こうの人たちと話をした際の一般的な印象として、彼らはけっこう私的成功派だと思います。私的成功と公的成功の両輪を目指すというよりは、もっとインディペンデントです。一方の日本人は、公的成功とは言えないかもしれませんが、よい意味でも悪い意味でも「和をもって尊ぶ」という感覚が強いですね。
- 安藤
- 公的成功には対象が必要ですから。
- 竹村
- 日本人はミッション・ステートメントでも、個人の価値観より他の人のことを立てたり、プライオリティでも重要事項を優先するというよりは、来たものすべてに対してイエスと言うのが美徳だと思っていたりします。
- 安藤
- それはありがちな(笑)。
- 竹村
- 狩猟民族と農耕民族の違いというのもあるかもしれません。実は、『7つの習慣』の中では、私的成功にあまり重きを置いていないと言えます。美徳的な意味ですが、むしろ、人とのつながりのほうに重きを置く。このあたりは、かなり日本人的感覚ではないかいと思います。
- 安藤
- ミッション・ステートメントって、私は『7つの習慣』で初めて知った言葉だと思うんですけど、米国の教育現場などではよく使われる言葉なんですか。
- 竹村
- ミッションという言葉自体、本来はクリスチャン用語というか、ミッション=教会だったりするので、単語としてはよく使われているでしょうね。もともと米国のベースにはクリスチャニズムがありますから、ビジネス向けの研修などで、「あなたのバリューって何ですか」などと聞くと、皆さん、けっこうするっと出るんですよ。

でも、日本人に同じことを聞いても、詰まってしまってなかなか出てこない。やはり、外国製のプログラムをそのまま日本に持ってきてもピンとこないようです。 - 安藤
- 自分の人生に対するクレドとかプリンシプルとか原則とかいわれても、日本では聞き慣れない人もまだ多いでしょうし、なかなかピンとこないでしょうね。
- 竹村
- ただ、クリスチャニズムに代わるものは、日本にもあったわけですよ。武家社会や武士道の時代には、そういう精神的な背骨のようなものが非常に大切にされていました。しかし、戦後の日本は、日本を日本たらしめてきた大切な精神性を、悪い意味での西洋化によって根こそぎ抜かれてしまった。おそらく、そういう状況すら受け入れてしまう国民性を見透かされて、敗戦国にもかかわらず、一国としての独立が認められたのではないかという気がしなくもありません。大切なもの、かけがえのないものを大切にしない生き方をしていると、価値観の基準が、お金とかポジションとか名誉とか、そういうものにだんだんすり替わっていきがちです。今の日本は、残念ながらそういう傾向が強くなっているような気がします。
●人生とは時間そのもの
- 安藤
- 親から受け継がれているもの、お袋の味ではないですが、決まったメニューやレシピはなくても確かに存在する不文律のようなものって、とても大切ですよね。
- 竹村
- そうですね。日本人がグローバルな社会に出ていくと「いい人なんだけど宗教観がない」ということでがっかりされることが多いんですよ。他の国にはしっかりした宗教観があって、その宗教観の中で学んできたことが、個々の思想なり価値観の土台になっていたりするものなのですが、残念ながら日本人にはそれが少ないのかもしれません。
そういうことをしつけてくれる親だったり、おじいちゃんおばあちゃんだったり、あるいはきちんと教えてくれる講師だったりメンターだったり。そういう存在がいれば、日本人の中にも個々のプリンシプルというものができていくのかもしれません。 - 安藤
- 私の祖父は戦前から進取の気性の持ち主で、今でいう起業家精神につながるものを私たちによく言い聞かせてくれました。
- 竹村
- それが安藤さんの中の価値観やプリンシプルになるわけですよね。それがない人たちは、いったい何を拠りどころにしたらいいのでしょう、ということになります。
- 安藤
- 今、私にとって最も身近なツールの一つが携帯とネットで、スマートフォン一つあれば、地図も見られて、ガイドブックもあって、翻訳もしてくれて、仕事だって旅だってできてしまう。じゃあ、これだけ便利になって、空いた時間をどう使っているのかというと、だらだらSNSを見たり、LINEで友達に写真やメールを送ったり。よりよく生きたいと思っているはずなのに、どうしてなんでしょうね。

- 竹村
- 私ども、フランクリン・コヴィー社の社名にある「フランクリン」って、実は、合衆国憲法の起草者、ベンジャミン・フランクリンから来ているのをご存じでしたか。
- 安藤
- アメリカ合衆国建国の父ですよね……全く知りませんでした。
- 竹村
- フランクリンは、時間=人生という定義をした人で、「人生を愛するものよ、時間を無駄にしてはならない。人生は時間そのものなのだから」という言葉を残しています。彼自身、非常に多才で活動的な人で、何のためにどう時間を使っていくのか、本当にシビアに捉えて、その通りに実行した人です。“Value of time”、時間の価値という表現をしていますが、時間に対する価値観そのものが、今の私たちとは感覚的に全く違うのかもしれません。
- 安藤
- 「時間は人生である」という言葉にはいろいろ考えさせられますね。自分の一生を80年と考えたら、もう人生の1/3は終えているのに、私はまだその“Value of time”というものがピンとこないという。
- 竹村
- 「7つの習慣」の中で最も多く使われている単語の1つに「自覚」という言葉があります。先入観とか思い込みをガラッと切り替えて、客観的に自分自身を見つめることを指す言葉なんですが。よく人生を80年になぞらえますけど、実はそれだけだと不十分で、普通に大学を出て、一般的な企業に入って、毎日2~3時間の残業をして、週休2日で、定年は65歳、80歳で人生の幕を閉じる人が、一生の間で仕事に使うことができた時間って、生涯の20%弱に過ぎないんです。
- 安藤
- そんなに。
- 竹村
- それなのに、週末が待ち遠しいだとかいって、1週間のうち、休日の2日間のために残り5日間を無為に過ごしているわけですよ。せっかく社会や周囲に対してよい影響を与え得る機会が与えられているのに。人生全体のたった20%くらいしかない貴重な時間なのに。と、考えてみると、なぜもっと意味のある時間の活かし方ができないのかと、目からウロコが落ちるのではないでしょうか。
- 安藤
- それを聞くと、なんだかすごくもったいない気持ちになりますね。