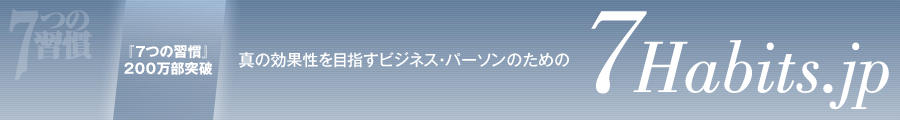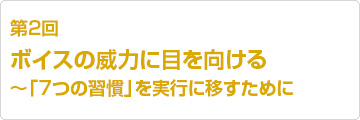●「ありのまま」を日本語にした、新訳版『7つの習慣』
- 竹村
- 安藤さんは、『7つの習慣』を読んでくださっているんですよね。
- 安藤
- はい、社会人なってからなので、2004〜5年くらいに。当時はビジネス誌とか、とにかくあちこちで見かけました。周囲からもジェームス・スキナーさんの合宿付きセミナーに参加したとか、セミナーに出たとか、そういう話をよく耳にしましたし、勝間さん含め多くのビジネスリーダーたちが『7つの習慣』に言及されていて、ベストセラーリストにも入っていたので、もうこれは……と(笑)。

- 竹村
- ありがとうございます(笑)。かなりメディアでの露出も多かった時期でしたね。
- 安藤
- それに乗じて読んだのですが、かなり厚めの本ですし、内容が難しくて、実はよくわからなかったんです。
- 竹村
- わかります。
- 安藤
- でも、『7つの習慣』が一つのきっかけになって、デール・カーネギー『人を動かす』とか、自己啓発系のかなり厚めの翻訳本を読むようになりました。ただ、当時の私には『7つの習慣』をしっかりとは読み解けなくて、「どんなことが書いてあるの?」って聞かれても、自分自身が本当にわかっていないので、しゃべっているうちによくわからなくなって、相手もぽかんとするような感じでした。
- 竹村
- 日本語に翻訳すると、どうしても伝わりにくくなってしまう部分もありますからね。それで昨年、新しい訳の完訳版をつくったんですよ。こちらは旧版と比べると、かなりわかりやすくなっていると思います。
- 安藤
- 書かれているものが本質的であればあるほど、抽象度が高ければ高いほど、ありのままではなく、自分の経験した世界を通して見ようとしてしまうんですよね。この対談を機に、ぜひ完訳版のほうで読み返してみたいなと思っています。
- 竹村
- それは嬉しいですね。
- 安藤
- 竹村さんが最初に『7つの習慣』を読んだときのご感想ってどんな感じでした?
- 竹村
- 確か、アメリカ人の友達に勧められて、原書を色鉛筆で線を引きながら読んだんですよ。でも、第2の習慣あたりで止まっちゃいました(笑)。私自身も、そういう経験をしながら、ここに辿り着いたというわけです。
- 安藤
- そもそも完訳版を出されるきっかけというのは何だったんですか。
- 竹村
- そうですね、1つは前回に訳したのがもう18年ほど前で、時代背景とか言葉に対する感覚が変わってきているということ。そこで、今回は本当の意味での完訳版をつくりたかったんです。可能な限り、訳者の意図というものを排して、英語をそのまま日本語に置き換えることを目指しました。

とにかく原書に忠実に。そして、日本語でわかりやすく。基準はこの二つだけです。一つの名詞に対して形容詞が3〜4個ついていたり、動詞に対して副詞がいくつも連なっていたりしても、雰囲気でまとめたりせず、対訳版ってありますよね、右のページに原文があって、左のページに逐語訳が、という。それに近い完成度を目指しました。したがって、コヴィー博士が書いたものがそのまま日本語になった、というわけです。 - 安藤
- 新訳といっても、日本向けの内容に変えたわけではなくて、原書に対する忠実性を増したということなんですね。
- 竹村
- ええ。ずっとそういうものをつくりたかったんです。二年前にコヴィー博士が亡くなったことを受けて、フェアウェルの思いも込めました。本当に莫大な時間と手間をかけて、昨年ようやく形にすることができました。
●顔のある本、顔のない本
- 安藤
- 私、自己啓発書の祖と言われる、エマソンの『自己信頼』という本がすごく好きなんです。100年近く前の本ですけど、オバマ大統領がバイブルにしていることでも有名です。この本、書き手が誰かということは特にフィーチャーされていなくて、著者の写真もないですし、いろいろなバイアスがかかってないんです。いい意味で、顔があるようでないような本だと思うんですね。聖書がその代表だと思うんですが、こういう本ほど長年読み継がれるのには何か理由があるのかなと。

その一方で、新訳の『7つの習慣』は、あえてコヴィー博士の写真とかパーソナリティを前面に出して、コヴィー博士の著作であることを強く押し出していますよね。これは、どうしてなんでしょう。 - 竹村
- そもそも、私どもの社名はフランクリン・コヴィーですから、やはりコヴィー博士の存在が土台になっているということが挙げられますね。ただ、実際にブランドとして強力なパワーを持っているのは「7つの習慣」のほうなんですよ。社名やコヴィー博士の名前よりも、まず「7つの習慣」として知られているわけです。
一方で、「7つの習慣」というのは、フランクリン・コヴィー社の基幹軸でありながら、あくまで全体の中の一部であって、すべてではないんです。同様に、『7つの習慣』という本も、コヴィー博士のすべてではないわけです。彼の芯にあるのはリーダーシップ論で、それをいかに発揮していくかというところで役に立つのが「7つの習慣」という位置づけなのです。したがって、「コヴィー博士が提唱しているリーダーシップ」というものをもっと前面に出していきたいという戦略もあって、今回は顔をつけたということになります。 - 安藤
- それは、日本の中でのことですか? それとも世界的に?
- 竹村
- 本国の米国では、あまり「7つの習慣」をフィーチャーしていないんです。基本、研修コンサルティングがメインの企業ですから、「7つの習慣」のエッセンスは、あくまでその中のパーツという位置づけになっています。本なども外部の出版社から出していますしね。一方、日本支社は、出版事業を組織の中に組み込んでいる唯一の国なんです。出版コンテンツに最も力を注いでいるのも、「7つの習慣」というブランドが他のどの国よりも強いのも、この日本というわけだからです。
そして、幼稚園児からリタイア年代の方まで、老若男女すべての方々に向けて、「自分が行きたい方向に向かって進んでいこう」というリーダーシップ論を提唱しているのは、世界中でコヴィー博士しかいないと思います。 - 安藤
- なるほど、そういうことなんですね。
●あなたの声を見出しなさい
- 竹村
- コヴィー博士は、『7つの習慣』の後に『第8の習慣』という本を書いています。
- 安藤
- まだ読んでおりません。一体、どんなことを主張された本なのでしょうか。
- 竹村
- 彼の考えというのは、大きく二つのパートに分かれるんです。パート1にあたるのが「私的成功」をいかに深めるか、そしてパート2が「公的成功」をいかに深めるか。『7つの習慣』でも、私的成功と公的成功について触れていますが、特に公的成功の部分にフォーカスしているのが『第8の習慣』というわけです。

その中で決定的なキーワードと言えるのが「ボイス」です。だから『第8の習慣』の第一部のタイトルが、“Find your voice”、あなたの声を見出しなさい、となっているんです。安藤さんも、ボイスについてはよくご存じですよね。 - 安藤
- 自分の心の声とか、天命というか、声に従って行動する、ということですよね。
- 竹村
- 人が生きていく上で最も大切にしていくべきもの。そうコヴィー博士が捉えているのが、まさにこのボイスなんです。
ジェームス・スキナーがコヴィー博士と会ったとき、「7つの習慣」って7個もあるけれど、簡潔に一言で表すなら「Be good、よい人になりなさい」だね、という話をしたそうです。“Be good”になっていくにはセルフ・リーダーシップが必要で、そのセルフ・リーダーシップを発揮していくためにボイスが不可欠。コヴィー博士が最も伝えたかったことは、このことなんじゃないかなと思うんですよ。 - 安藤
- そういうコヴィー博士の思いの強さって、どこから来るものなんでしょうね。
- 竹村
- 実は、コヴィー博士のミッション・ステートメントって、すごく単純なんですよ。“Release human potential”、人間の可能性を解放する、という。それをいかに実践していくか、その方便の1つとして「7つの習慣」が役に立つ。いってしまえば、ボイスもリーダーシップも“effective”も偉大さも、結局は全部この“Release human potential”につながっているんです。
一人ひとりが、自分の使命とは何なのかを自覚し、その実現に向けて自分で自分を導いていく。それが人としての理想的なあり方であり、すべての人がそうできるよう、考え、サポートしていくこと。それがコヴィー博士の目標だったように思います。
そうした思想リーダーとしてのコヴィー博士の強力なリーダーシップをフィーチャリングして、その存在を前面に押し出していくことは、他に替えられない大きな意味があると考えています。