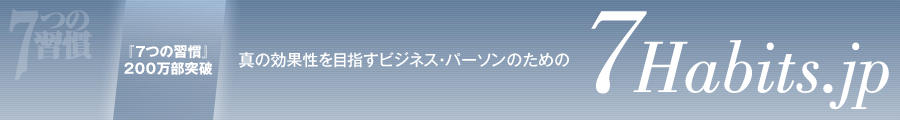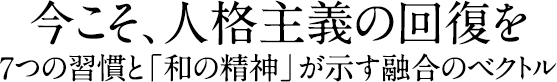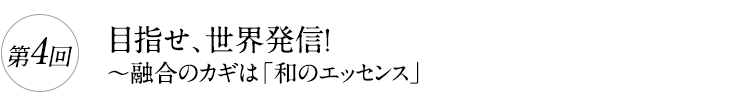●公の精神を持つ日本人は、まるでキリストか仏陀のよう?
- 竹田
 東日本大震災の映像を見たフランスの友人がすごく印象的なことを言ってくれたんです。日本の被災者全員がキリストのように見えたと。もう1人、ミャンマー人の女性も、全員が仏陀のように見えたと、同じようなことを言っていました。これってすごいことですよね。
東日本大震災の映像を見たフランスの友人がすごく印象的なことを言ってくれたんです。日本の被災者全員がキリストのように見えたと。もう1人、ミャンマー人の女性も、全員が仏陀のように見えたと、同じようなことを言っていました。これってすごいことですよね。- 西川
- 少し褒めすぎかもしれませんが、嬉しいことですね。
- 竹田
- アメリカを例に挙げれば、ハリケーンで避難した住人がやっと戻ってきたらショッピングセンターが襲撃されていたとか、そういうケースをさんざん見てきていますから。何か困難なことが起こったとき、日本人は自分のことよりもまず、皆のために自分が何ができるかを考え始める。そういう公の精神を1人ひとりが持っている。これこそ、日本人の大きな特徴だと思うんです。
- 竹村
- おっしゃるとおりですね。
- 竹田
- 結局、イエス・キリストや仏陀の言っていることを社会として実践してきたか否か。それが日本と諸外国の違いだと思うんです。
- 西川
 アメリカの社会というのはある種カオスですから、混沌の中に秩序をつくらないと、砂のように崩れてしまう脆さを抱えていますよね。そうした土台の上に構築した社会であるからこそ、7つの習慣のような結晶した考え方が必要であり、また常にそういったことを言い続けなければ維持できないという事情がある。逆に、そこから私たち日本人が学ぶべき点も大いにあるような気がします。
アメリカの社会というのはある種カオスですから、混沌の中に秩序をつくらないと、砂のように崩れてしまう脆さを抱えていますよね。そうした土台の上に構築した社会であるからこそ、7つの習慣のような結晶した考え方が必要であり、また常にそういったことを言い続けなければ維持できないという事情がある。逆に、そこから私たち日本人が学ぶべき点も大いにあるような気がします。
日本人が空気として持っていたもの、でも今や社会の変化の中で失われつつあるもの。それを取り戻そうとするときに『7つの習慣』という本は、私たちの中の眠っていた細胞を生き返らせるメディアになり得る存在だと思います。- 竹田
- 特に、7つの習慣というアメリカ人の目を通して入ってくる日本の長所というのは、非常に効くような気がします。日本人って、ペリー来航以来、西洋から言われると必要以上に聞く耳を持ってしまうところがありますから(笑)。
逆輸入じゃないですけど、そうやって欧米のほうからさまざまなメッセージを出してくれることで、日本人が気づくこともたくさんあるでしょう。そういう面でも、7つの習慣というのは非常に大きな要素になり得ますし、震災を経た今、もう1回読み直すと、また違った視点で読めるんじゃないかと思います。
●大自然に感謝する日本vs創造主に感謝する欧米
- 西川
- 江戸の末期、植物研究の大家だったイギリス王立植物園のロバート・フォーチュンという人が来日しているんですが、彼は、大名やお金持ちの庭が美しいだけじゃなく、貧しい長屋の借家住まい、今でいえば四畳半一間に家族で住んでいるような家であっても、皆が朝顔などの花を愛でる心を持っていることに「考えられない」と驚いているんです。当時のイギリスは産業革命で蒸気機関とか技術的な面で世界のトップに立っていたけれど、少なくとも草花を愛でる習慣を見る限り、日本の庶民の民度のほうがロンドンのそれより高いと、書いています。
盆栽なんかを見てもわかるように、自然との共生、環境問題などについて、もともと日本人の意識とか感覚というのは非常に高いものがありますからね。 - 竹田
 日本の場合、大自然に対する価値観が欧米と全く違うんですよね、韓国や中国とも全然違うんですけど。その根底にはやはり宗教観の違いがあると思います。
日本の場合、大自然に対する価値観が欧米と全く違うんですよね、韓国や中国とも全然違うんですけど。その根底にはやはり宗教観の違いがあると思います。
たとえば、日本人にとって自然とは恵みを与えてくれる存在で、大自然に神の姿を見ている。一方、キリスト教的な世界観では、「神は自らの姿に似せて人を創った。そして人に大自然の管理を委任した」と聖書にありますから、人間というのは神に代わって大自然を管理する役割を与えられている存在なわけです。
日本人は食材に対しても感謝をしますよね。「いただきます」というのは、「魚さん、動物さん、申しわけないけどあなたの命をいただきます。その代わり、私はあと1日生き永らえさせていただきます、ありがとう」ということですし。
逆にキリスト教のほうは、「君たちは私に食べられるために生まれてきたわけで、食べてあげるから感謝しなさい」というスタンスですから(笑)。欧米人の場合、感謝するとしたら、食材ではなくて、宇宙の外にいる神に対して感謝します。神が人間を創ってくださったこと、そして大自然の管理を委任してくださったことへの感謝ですね。神を差し置いてモノに感謝を捧げたりしたら、それは創造主である絶対神への冒涜になってしまう。- 竹村
 最初の部分がこれだけ違えば、気質とか価値観だって相当違ってきますよね。
最初の部分がこれだけ違えば、気質とか価値観だって相当違ってきますよね。- 西川
- 日本人は大自然の恵みをいただいて、生かされている立場なので、自然に対しても、当然、腰が低いわけです。和を大切にして、皆で協力体制を敷いて、ありがとう、ありがとうと、天地の神に感謝をする。欧米の場合は、まず自分が何をするかが重要ですから、パワフルでちょっと強引になる。女性的、男性的な違いともいえるでしょうか。大自然をどう捉えるかによって、ここまで差が出るんですね。
●価値観の輸入⇒逆輸入⇒そして双方向発信へ
- 竹田
- でも、日本的価値観とキリスト教的価値観って、解釈によっては融合できると思いますよ。一見、水と油のように見えますが、キリスト教的世界観を壊さずに、日本的価値観を持ち込むことは可能なんじゃないかと。
神は自らの姿に似せて人間を創った、そして人間に大自然の管理を委任した。そのとき人間は「神に代わって大自然を統率する」のではなく、「神様の命令をいただいたので大自然を管理させていただく」という立場をとることにすれば、それだけでいいように思うんです。
神から役割をいただいた自分らは大自然より偉い、という上から目線ではなく、むしろ下から「大自然がうまく機能するように、人間ごときで申し訳ないのですが、何かお手伝いができればということで、うまく調和がとれるように統制させていただきますね」と。そうすれば、大自然の恵みに感謝をしたからといって、別に神との関係が絶たれることにはならないんじゃないかと思うんです。
 たとえば、初日の出に手を合わせる、拝む。日本人にとっては当たり前のことなのに、欧米にはない感覚なんですね。同じ東洋の中国や韓国でもあり得ないことのようですが。私たち日本人は、太陽をただの天体ではなく霊的なものとして見ているからこそ、拝むという発想が自然に出てくる。しかし、それらも神が創り出したものであるならば、そこに価値があって尊いものだと思ったり、慈しむ気持ちを持ってもいいはずですよね。
たとえば、初日の出に手を合わせる、拝む。日本人にとっては当たり前のことなのに、欧米にはない感覚なんですね。同じ東洋の中国や韓国でもあり得ないことのようですが。私たち日本人は、太陽をただの天体ではなく霊的なものとして見ているからこそ、拝むという発想が自然に出てくる。しかし、それらも神が創り出したものであるならば、そこに価値があって尊いものだと思ったり、慈しむ気持ちを持ってもいいはずですよね。 - 西川
- マザーネイチャーとか英語でもいいますし、欧米人にもその感覚が全く理解できないわけではないように思いますけどね。「ユビキタス」という言葉もネットなどでよく使われますが、本来は「神はあまねく存在する」という意味ですから、いわば八百万の神の考え方に近いのかもしれませんし。
欧米人にとっては木の葉がこすれあう音や虫の鳴き声はノイズでしかないそうですが、日本人はそれを美しいと感じる感性を持っている。自然と同じ目線で生きているといいますか、日本人のそういう特異な部分が、7つの習慣を通して世界中のさまざまな価値観をつないでいくことに貢献できるかもしれないですよね。 - 竹田
- 本当にそうですね。そういったものすべてが、たぶん、和の精神というところに行き着くように思うんですが、和の精神って慈しみの気持ちだと思うんです。他者に対してもそうだし、大自然に対してもそうだし。いろいろなものを尊重するからこそ、自分のことも尊重できる。だから調和をとろうとするし、皆のために何ができるかを考える。それが日本人であり、和の精神なんです。
 コヴィー博士が、本来であれば7つの習慣は東洋から出るべきだったとおっしゃっていたという話がありましたが、そこに僕のほうで1つ付け加えさせていただけるならば、日本オリジナルの発想として、大自然に感謝するという要素をぜひ、お願いしたいですね。せっかく7つの習慣がこれだけ日本に根付いてきたわけですから、これからは双方向で、こういう和のエッセンスを7つの習慣を通じて、日本から世界に発信していただけたらありがたいことだと思います。
コヴィー博士が、本来であれば7つの習慣は東洋から出るべきだったとおっしゃっていたという話がありましたが、そこに僕のほうで1つ付け加えさせていただけるならば、日本オリジナルの発想として、大自然に感謝するという要素をぜひ、お願いしたいですね。せっかく7つの習慣がこれだけ日本に根付いてきたわけですから、これからは双方向で、こういう和のエッセンスを7つの習慣を通じて、日本から世界に発信していただけたらありがたいことだと思います。 - 西川
- 竹田先生でなければお考えいただけない、非常に重要な視点を教えていただきました。今日もまた元気をいただきました。ありがとうございます。
- 竹村
- 貴重なお話の数々、たいへん勉強になりました。ありがとうございました。