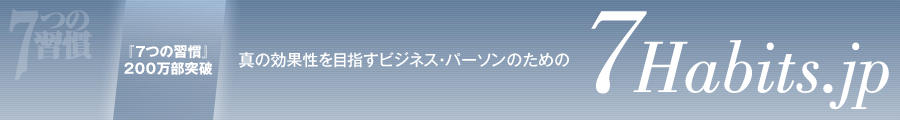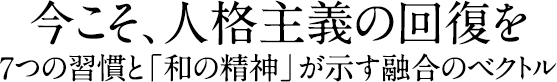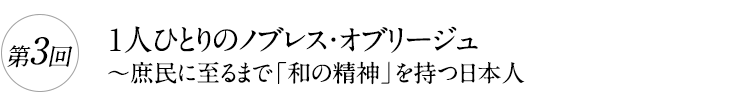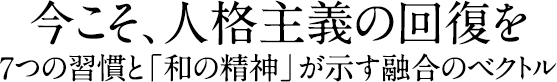
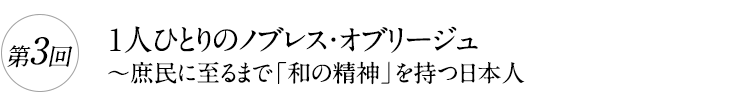
●日本から発信されるべきだった7つの習慣
- 西川
- 竹田先生は明治天皇の玄孫に当たられるわけですが、明治天皇、皇太后がおっしゃっていることにも、私は7つの習慣と通じるものがあるような気がしているんです。というのも、すごく仕事で悩んでいるとき、たまたま明治天皇の御製と皇太后の御歌を、拝見しましてね。
 明治天皇の御製は「ならび行く 人にはよしや 後るとも 正しき道を ふみな違へそ」。自分が歩むのが遅れたとしても、正しい道を踏み違えないようにということですね。皇太后の御歌のほうは、「ひとすじの その糸口もたがふれば もつれもつれてとくよしぞなき」。糸も1つ間違えてしまうとぐちゃぐちゃにもつれてほどくこともできなくなってしまう。だから1つひとつ、コツコツとやっていかなければいけないという内容です。
明治天皇の御製は「ならび行く 人にはよしや 後るとも 正しき道を ふみな違へそ」。自分が歩むのが遅れたとしても、正しい道を踏み違えないようにということですね。皇太后の御歌のほうは、「ひとすじの その糸口もたがふれば もつれもつれてとくよしぞなき」。糸も1つ間違えてしまうとぐちゃぐちゃにもつれてほどくこともできなくなってしまう。だから1つひとつ、コツコツとやっていかなければいけないという内容です。
両方とも不思議なくらい7つの習慣と同じことをおっしゃっていて、ああ、やっぱりそうなんだなと。それがわかって、私はものすごく救われたんです。大事なのは本質的なことであり、それは結局のところ全部同じものなんだと。
- 竹村
- コヴィー博士は生前、「7つの習慣は、本当は西洋ではなく東洋から出るべきものだった」と私におっしゃったことがあるんです。それがある意味、すごく嬉しいのとすごく悔しいのと、私には両方の気持ちがありましてね。
こういう素晴らしい文化を持っている国の人間としては、それが今、まるで逆輸入されているような状況から、今後どうやって、主体的に発信していくかを考えるわけです。そこで必要になるものは何かというと、「徳」というものに行きつくのではないかと思うのです。
この、日本人だけが本質的に備えてきたと思える徳というもの。先進国の中でも、日本という国はユニークな立場にありますから、これから中国とかいわゆる第三国が同じように欧米化していった場合、果たして地球がどんな風になってしまうのか、とても不安になるんです。そうならないよう、新しい道しるべのようなものを指し示していくのが、徳を持った日本という国の役割なのかなと考えたり。そこにも、また7つの習慣というものが、1つの媒介として作用するんじゃないかなという気がしているんですが。
- 竹田
- 『7つの習慣』と出会った当時は全くそういう感覚はなかったんですが、ここ数年、『7つの習慣』って、日本人が大切にしてきた「和の精神」というものと深くつながっているんじゃないかなと思うようになりました。
日本人の幸福感というのは、自分がどうなるかということよりも、他者に何を与えられるかが優先される。だから、他者のために生きる、というのが美しい生き方とされてきて。それが封建的でつまらない考え方のように扱われていたところに、東日本大震災が起きて、目に見えないつながりを大切にする、日本人の絆というものが、再び見直されつつあるような気がしています。
- 竹村
- あの大震災が私たちに与えた影響には測り知れないものがありますね。
●和の精神と7つの習慣の共通項
- 竹田
 日本人の考え方というのは、社会全体、民族の発想そのものが、一歩下がって自分のことは後、なんですよね。他人のために何ができるか、それがすなわち自分の幸せであるという。
日本人の考え方というのは、社会全体、民族の発想そのものが、一歩下がって自分のことは後、なんですよね。他人のために何ができるか、それがすなわち自分の幸せであるという。
といっても、ただやみくもに他者を優先するわけではなく、さまざまな役割を認識しながら、自分は家族のために何ができるか、最後は国のために何ができるか。そういうことを含めて、いろいろな次元で1人ひとりが自分らしく振る舞ってきたに過ぎないのですが。そうしたものが日本の歴史であると捉えたとき、7つの習慣がこれだけ普遍的に求められ理解されているという事実と、けっこう通じるものがあるのかなと。- 竹村
- 7つの習慣はもともとアメリカから来たものですから、文化的に、狩猟民族のインディペンデントな感じと、我々農耕民族の和を大切にする部分のギャップというのはあると思うんです。たとえば、7つの習慣でいうところの「私的成功」については欧米人のほうが得意でしょう。でも、日本人は「公的成功」みたいなところを本質的にすごく大切にしてきた民族ですよね。
しかし戦後は、核家族化、さらにインターネット時代が到来して、欧米主義のいい部分だけでなく悪い部分もそのまま取り込んでしまって、自分さえよければいい、というような価値観が広がっていたところに、リーマンショックや大震災が起きた。今、日本人の価値観も、まただんだんと変わりつつある時期ですよね。
 そうした相反する文化や価値観もすべて含めて、パッケージングで教えてくれるのが7つの習慣なのかなと。最終的にコヴィー博士が目指すところは、竹田先生がおっしゃったこととまさに同じ、「貢献」なんですよ。最終的には、世のため人のために自分に何ができるのか、そこを最後の最後まで突き詰めていく。でも、あくまでスタートは、自分自身の人格を磨くことから。そうしないと、決して貢献には行き着かない。それが7つの習慣の考え方なんです。
そうした相反する文化や価値観もすべて含めて、パッケージングで教えてくれるのが7つの習慣なのかなと。最終的にコヴィー博士が目指すところは、竹田先生がおっしゃったこととまさに同じ、「貢献」なんですよ。最終的には、世のため人のために自分に何ができるのか、そこを最後の最後まで突き詰めていく。でも、あくまでスタートは、自分自身の人格を磨くことから。そうしないと、決して貢献には行き着かない。それが7つの習慣の考え方なんです。
- 西川
- コヴィー博士は、日本的あるいは東洋的な和の精神のようなものが共通項である、というようなことも話しておられましたよね。7つの習慣でいう「Win-Win」とか「シナジー」の思想というのは、もともと日本の中にあったものなのに、それが長らく失われていて、もう一回その原点に戻ってくるのに不可欠なキーワードとして「私的成功」と「公的成功」の両立があり、そのためには個々の人格、どう生きるか、何が幸せなのか、というところを突き詰めてゆく必要がある。
竹田先生が今、全国を駆け巡って教えておられることも、基本的にはたぶんそういうことですよね。
- 竹田
- そうですね。失われゆく日本のよさを、少しでも残していきたいなと。僕の場合、皇室が未来永劫しっかり残ってほしいというところから発しているんですけど。個人主義が極まると、皇室なんてどうでもいい存在になってしまいかねませんから、たとえば古事記のようなものを通じて、日本人のアイデンティティについて知ってもらって、それが残せるようになったらいいなと考えているんです。
- 竹村
- そこがないと、自分が何者なのか、わからなくなってしまいますものね。
●衣食足りずとも礼節を知るのが日本人
- 竹村
- 先ほど、明治天皇の御製に勇気づけられたという西川さんのお話がありましたが、日本という国の成り立ちから考えたらそれも当然で、本来、天皇とはそういう役割を担う存在でもあるわけですよね。
- 竹田
- ヨーロッパではそれに近い役割を貴族が担っていました。ところが、幕末、日本に着任したアメリカ外交官ハリスは、「日本人は全員、生まれながらにして貴族の器を持っている」と驚いたといいます。
 彼も最初は日本人なんて野蛮人だろうと見下していたわけです。ところが、周辺の農村や漁村を視察してみると、貧しいけれど皆豊かな笑顔が絶えず、着ているものはボロながらきっちり着こなしていて、礼儀正しく、皆で協力し合いながら畑は隅々まで見事に耕作されている。この人たちはどれだけ働き者なのか、と感嘆せざるを得なかった。しかも、他人を思いやる気持ちとかボランティア精神のようなものまで皆が共有している。庶民がこれほど豊かに暮らしている場所は、世界でもおそらく例がないのでは、と書き記しています。
彼も最初は日本人なんて野蛮人だろうと見下していたわけです。ところが、周辺の農村や漁村を視察してみると、貧しいけれど皆豊かな笑顔が絶えず、着ているものはボロながらきっちり着こなしていて、礼儀正しく、皆で協力し合いながら畑は隅々まで見事に耕作されている。この人たちはどれだけ働き者なのか、と感嘆せざるを得なかった。しかも、他人を思いやる気持ちとかボランティア精神のようなものまで皆が共有している。庶民がこれほど豊かに暮らしている場所は、世界でもおそらく例がないのでは、と書き記しています。
彼だけじゃなく、当時、日本を訪れた外国人たちは皆、同じように驚いたようですね。ヨーロッパでは、庶民は自分の生活で精一杯、ボランティアとか貢献といった意識は貴族しか持っていないもの、というのが共通の認識でしたから。
- 竹村
- なるほど、ノブレス・オブリージュですね。
- 竹田
- まさに、衣食足りて礼節を知る、というわけです。だから、スラム街に住んでいる人には礼儀なんかない、というのが欧米の常識で、貧困が犯罪にそのまま結びつく。一方、日本人は衣食足りずとも礼節だけは切らさない。どんなに貧乏でもそれだけは口にしてはいけないとか、やってはいけないという価値観のようなものを、皆が当たり前のように共有しているのが日本という国なんです。
僕が一番象徴的だなと思うのは、無人の野菜売り場ですね。商品が置いてあって、現金が置いてある。なのに、誰も悪さをしないなんて他の国ではありえないことでしょう。
- 西川
- 確かに日本でしか成り立たない販売スタイルですよね。
- 竹田
- 日本人というのは、貧富や階級の差に左右されることなく、庶民や貧乏人に至るまで、そういう感覚が隅々まで息づいている国民だということがいえると思います。
 明治天皇の御製は「ならび行く 人にはよしや 後るとも 正しき道を ふみな違へそ」。自分が歩むのが遅れたとしても、正しい道を踏み違えないようにということですね。皇太后の御歌のほうは、「ひとすじの その糸口もたがふれば もつれもつれてとくよしぞなき」。糸も1つ間違えてしまうとぐちゃぐちゃにもつれてほどくこともできなくなってしまう。だから1つひとつ、コツコツとやっていかなければいけないという内容です。
明治天皇の御製は「ならび行く 人にはよしや 後るとも 正しき道を ふみな違へそ」。自分が歩むのが遅れたとしても、正しい道を踏み違えないようにということですね。皇太后の御歌のほうは、「ひとすじの その糸口もたがふれば もつれもつれてとくよしぞなき」。糸も1つ間違えてしまうとぐちゃぐちゃにもつれてほどくこともできなくなってしまう。だから1つひとつ、コツコツとやっていかなければいけないという内容です。 日本人の考え方というのは、社会全体、民族の発想そのものが、一歩下がって自分のことは後、なんですよね。他人のために何ができるか、それがすなわち自分の幸せであるという。
日本人の考え方というのは、社会全体、民族の発想そのものが、一歩下がって自分のことは後、なんですよね。他人のために何ができるか、それがすなわち自分の幸せであるという。 そうした相反する文化や価値観もすべて含めて、パッケージングで教えてくれるのが7つの習慣なのかなと。最終的にコヴィー博士が目指すところは、竹田先生がおっしゃったこととまさに同じ、「貢献」なんですよ。最終的には、世のため人のために自分に何ができるのか、そこを最後の最後まで突き詰めていく。でも、あくまでスタートは、自分自身の人格を磨くことから。そうしないと、決して貢献には行き着かない。それが7つの習慣の考え方なんです。
そうした相反する文化や価値観もすべて含めて、パッケージングで教えてくれるのが7つの習慣なのかなと。最終的にコヴィー博士が目指すところは、竹田先生がおっしゃったこととまさに同じ、「貢献」なんですよ。最終的には、世のため人のために自分に何ができるのか、そこを最後の最後まで突き詰めていく。でも、あくまでスタートは、自分自身の人格を磨くことから。そうしないと、決して貢献には行き着かない。それが7つの習慣の考え方なんです。 彼も最初は日本人なんて野蛮人だろうと見下していたわけです。ところが、周辺の農村や漁村を視察してみると、貧しいけれど皆豊かな笑顔が絶えず、着ているものはボロながらきっちり着こなしていて、礼儀正しく、皆で協力し合いながら畑は隅々まで見事に耕作されている。この人たちはどれだけ働き者なのか、と感嘆せざるを得なかった。しかも、他人を思いやる気持ちとかボランティア精神のようなものまで皆が共有している。庶民がこれほど豊かに暮らしている場所は、世界でもおそらく例がないのでは、と書き記しています。
彼も最初は日本人なんて野蛮人だろうと見下していたわけです。ところが、周辺の農村や漁村を視察してみると、貧しいけれど皆豊かな笑顔が絶えず、着ているものはボロながらきっちり着こなしていて、礼儀正しく、皆で協力し合いながら畑は隅々まで見事に耕作されている。この人たちはどれだけ働き者なのか、と感嘆せざるを得なかった。しかも、他人を思いやる気持ちとかボランティア精神のようなものまで皆が共有している。庶民がこれほど豊かに暮らしている場所は、世界でもおそらく例がないのでは、と書き記しています。