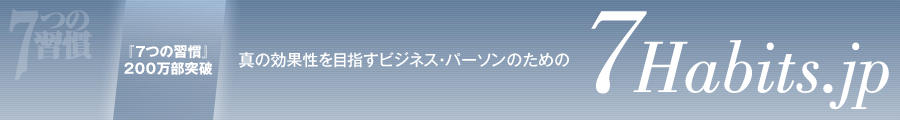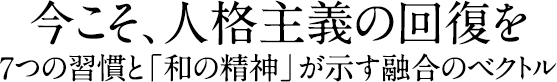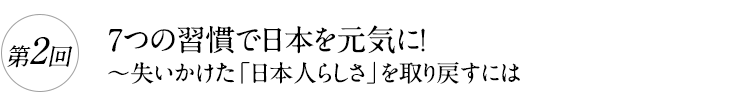●日本人に生まれてよかったと思える歴史教育を
- 西川
- 今、日本人はすごく自信失っていますよね。私たちが自信を回復するには、どんなことが大事になるでしょうか。
- 竹田
- 敗戦後、GHQの占領政策の影響でしょうが、「日本にはこういういい部分がある」ということを言いづらい時代がずっと続いていたように思うんです。
- 竹村
- 洗脳といったら言いすぎかもしれませんが、確かに効果てきめんでしたね。その影響が未だ続いているわけですから。
- 竹田
 当時のGHQの面々だって、戦後60何年経ってもまだ効いているなんて、とても信じられないでしょう。特に影響が大きいのが学校教育で、古事記や神話、神道については教えてはいけないことになっています。天皇についても国民から尊敬される部分は教えてはいけない。そういう教科書の検閲基準をGHQはつくったんですよ。戦後、どこかで見直されてもよさそうなものですが、一度できた空気というのはなかなか崩れないもので。
当時のGHQの面々だって、戦後60何年経ってもまだ効いているなんて、とても信じられないでしょう。特に影響が大きいのが学校教育で、古事記や神話、神道については教えてはいけないことになっています。天皇についても国民から尊敬される部分は教えてはいけない。そういう教科書の検閲基準をGHQはつくったんですよ。戦後、どこかで見直されてもよさそうなものですが、一度できた空気というのはなかなか崩れないもので。
そうなると、日本古来の美点のようなものをちょっとでも褒めると「軍国主義」と言う人が出てくる。たとえば、教科書に歴代の天皇の美しい話を入れようとすると、天皇賛美だの軍国主義だのと言われてしまうんです。- 竹村
- なるほど。
- 竹田
- 物事には光の部分と影の部分があって、日本にもいいところ悪いところの両面があるのに、いいところについては全く教えてこなかった。でも、嘘をついてまで否定する必要はないはずですよね。いい点も悪い点も含めて、こういう歴史があったということを若い人たちが知るだけでも、日本人に生まれてよかったなと思えるようになると思うんですけれど。
まず、今の若い人は建国の経緯を知らないですよね。もちろん、誰が建国したかとか、一応の成り立ちは歴史の教科書に書いてありますけど、日本ってすごいなと思えるような記述は消されています。だから、自分の祖国の歴史を学ぶことほどワクワクドキドキすることはないはずなのに、日本の歴史を勉強していても面白くないんですよ。歴史という教科に人気がないのは、たぶん、こういうことじゃないかと思っています。 - 西川
- ただ年号を覚えるだけ、というイメージが強いかもしれませんね。
- 竹田
- そうなんですよ、暗記だけで、ストーリーとか民族の情緒のようなものが欠落しているんです。
でも、東日本大震災の後、日本人が日本のことを学び直そうというブームが、戦後、初めて起きました。安倍総理も教科書を変えていこうと頑張っていますし、ようやく日本人が誇りを取り戻せる環境になりつつあるのかなと思いますね。
●神話を学ばなかった民族は例外なく滅びている
- 西川
 イギリスの歴史学者アーノルド・トインビーが「神話を学ばなかった民族は例外なく滅びている」と指摘していますよね。竹田先生もずっと同じことをおっしゃっていて、自分自身が何者なのか、いったいどこから来てどこに向かおうとしているのか、それが曖昧だと人間ってとても不安になると思うんです。戦後からこっち、こういうまさに人格の根本的な部分、背骨にあたる部分が、私たち日本人からなくなってしまっていたのかもしれません。
イギリスの歴史学者アーノルド・トインビーが「神話を学ばなかった民族は例外なく滅びている」と指摘していますよね。竹田先生もずっと同じことをおっしゃっていて、自分自身が何者なのか、いったいどこから来てどこに向かおうとしているのか、それが曖昧だと人間ってとても不安になると思うんです。戦後からこっち、こういうまさに人格の根本的な部分、背骨にあたる部分が、私たち日本人からなくなってしまっていたのかもしれません。- 竹田
- 神話というのは民族のアイデンティティそのものです。合理主義が徹底しているアメリカでも、ちゃんと神話は教えているくらい、科学的な視点とはまた別の重要なものが含まれている。フィクションだから読む価値がないなんていう人もいますが、そんなことをいったら世界中の文学作品は全部ゴミになっちゃいますから。やはり、自分が何者であるかを知るためには、日本人として神話くらい知らないとダメなんじゃないかと思うんですけど。
- 西川
- それが、竹田先生の『日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか』(PHP新書)という大ベストセラーにつながっていくわけですね。
竹村さん、御社もやはり、7つの習慣やフランクリン・プランナーを通じて、とにかく日本を元気にしていこう、というお気持ちでやってこられたように拝察しますが、今の竹田先生のお話と通じる部分をお感じになりませんか。 - 竹村
- 確かにそうですね。コヴィー博士は残念ながら去年亡くなってしまったんですが、そもそも、彼がなぜ『7つの習慣』を書いたのかというと、近年はすぐにスキルやテクニックを身につければ成功できるという、いってみれば「個性主義」の思想が蔓延しているけれど、果たしてそうだろうか。本当の意味で成功するためには、表面的な技術より、人としてこうあるべきという人格の部分に目を向けるべきではないだろうかと、そういうことだったと思うんです。
 今の日本人は欧米的な個性主義にすっかり心を奪われてしまっていますが、コヴィー博士が私たちに伝えようとしている人格主義的な要素というのは、アメリカ人のコヴィー博士に指摘されるまでもなく、私たち日本人の中に古くから根づいているものであり、コヴィー博士はもちろん、そのことに気づいておられました。
今の日本人は欧米的な個性主義にすっかり心を奪われてしまっていますが、コヴィー博士が私たちに伝えようとしている人格主義的な要素というのは、アメリカ人のコヴィー博士に指摘されるまでもなく、私たち日本人の中に古くから根づいているものであり、コヴィー博士はもちろん、そのことに気づいておられました。
戦争には勝ったものの、アメリカとしてはこういう日本人の精神性みたいなものが怖かったんじゃないでしょうかね。だから、それが復活して盛り返してこないようにGHQが画策した面があるように思うんです。
●日本人が本来持っている人格を取り戻そう
- 竹村
- 今度、『7つの習慣』を新訳で出版することになったのですが、現在の副題の「成功には原則があった!」というのは、実は日本側で勝手につけたものなんですね。オリジナルのサブタイトルは、英語版の表紙にも書かれていなくて、中のほうにちらっと書かれているので、皆さん、あまり気づかないんです。で、その副題を日本語に直訳すると、「人格主義の回復」。つまり、それが『7つの習慣』のテーマというわけです。
- 竹田
- ということは、最初の「第一の習慣」にある「主体性を発揮する」というのが根っこになるんですね。
- 竹村
 そうなんです。竹田先生は本文中に出てくるアメリカの格言を覚えていらっしゃるでしょうか。
そうなんです。竹田先生は本文中に出てくるアメリカの格言を覚えていらっしゃるでしょうか。
「思いの種を蒔いて習慣を刈り取り、習慣の種を蒔いて人格を刈り取り、人格の種を蒔いて人生を刈り取る」
まず、人格の前に習慣がある。人格を磨くには、よりよい習慣を身につけましょう、と。それが、まさに7つの習慣なんですね。
どうしても、この習慣をやったら成功する、というような短絡的な捉え方をされがちなのですが、本当の価値は人格主義にこそある。そして、私たち日本人は、もともと日本人が持っているものを回復していけばいいのですよ、ということを今、どうしても伝えたかったのです。それが今回、新訳を出す上での一番大きな目的、テーマなんです。- 竹田
- それを伺うと、本を読む姿勢が変わりますね。中身を読めば、「私的成功」「公的成功」について語られていますし、決して金持ちになりたいとか、短絡的な成功のためのバイブルではないことがわかりますが、最初はどうしても「成功するための秘訣がここに書かれている」ってところで見ちゃいますから(笑)。
そういう意味では、入口というか、パッと目に入る装いの部分が変わることで、かなり読み手の姿勢が変わるでしょうね。特に、この人格主義というのは、あの震災を経験した今だからこそ、読み手に響くと思います。 - 竹村
- 私たち日本人がもともと持っていた人格、人としてどうあるべきなのかというスタンス、そこを大切にしていくというのが、「日本を元気にする」ための一番の押しどころのボタンなのかなと個人的には思っていまして。そこに7つの習慣が貢献させていただけることがあるはずだと考えています。