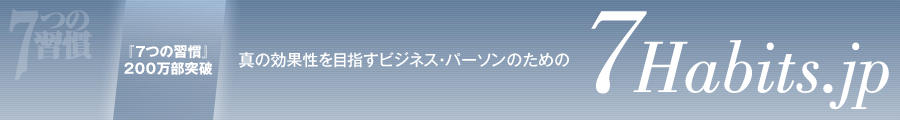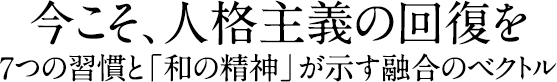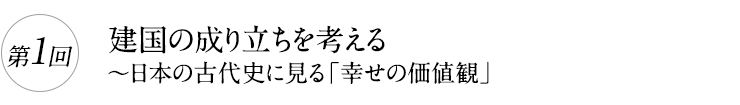●歴代天皇のワークライフ・バランス
- 竹村
- 竹田先生は『7つの習慣』をお読みくださっているそうですね。あの中で、先生が最も大切にしておられるのはどの部分になりますか。
- 竹田
 役割というか、家族の一員であるということ、会社の一員であるということ。その役割をそれぞれ考えるという部分ですね。
役割というか、家族の一員であるということ、会社の一員であるということ。その役割をそれぞれ考えるという部分ですね。
普段はどうしても自分中心の視点で考えるじゃないですか。でも、自分が実はいろいろなグループに属していて、それぞれ大切な役割を担っていること。そして、週に1回、その役割を具体的な行動に落とし込んでいくということ。『7つの習慣』を読んで初めて知ったことなので、気づくことがたくさんありました。これをやっていると、目の前の忙しさにかまけて、大切な役割をうっかり置き去りにするということがなくなると思うんですよね。- 西川
- 竹田先生のご専門でもある国史的な観点からご覧になると、7つの習慣というのはどのような印象になりますか。
- 竹田
- たとえば、歴代の天皇とか英雄には「家庭を治められない者は国を治められない」みたいな一貫した考え方があるんですよ。仁徳天皇とかオオクニヌシノミコトとか大舞台で活躍していますけど、実は家庭内ではいろいろな鬱憤があって(笑)、それを上手に乗り越えていくわけです。国を守るためなら家はどうなってもいい、とはならなくて、ちゃんとバランスをとっている貴姿が描き出されているんです。7つの習慣の役割というのも、そういう感覚なんだろうと僕は捉えています。
- 竹村
- 天皇も大変だったんですね(笑)。今風にいえば、ワークライフ・バランス。社会以前に家庭があって、家庭以前に自分自身がある。だから、まずは自分をマネジメントしましょう、という7つの習慣の考え方にも合致するものですね。自分をちゃんとコントロールし、マネジメントし、セルフ・リーダーシップを発揮できるようになって初めて、家庭が変わり、社会の中で影響力を発揮できるようになる。このことを7つの習慣では「インサイド・アウト」と呼んでいます。
もしかしたら、こういう考え方もかつては当たり前だったのかもしれませんが、今ではすっかり忘れ去られてしまって、むしろ逆のスタンスが常識にすり替わってしまっています。そんな現状に対する警鐘として、7つの習慣というものが存在しているのかな、と感じることがあります。
●日本の建国精神=個々の人格の尊重
- 西川
 竹田先生は、国内のホテルの部屋に聖書や仏典は置いてあるのに、なぜ古事記が置かれていないのか、と指摘されていますが、本当に不思議なことですよね。古事記や日本書紀は、日本の歴史、民族、あるいは文化の聖書のようなものなのに、その存在がすっかり忘れ去られているのは、どうしてなんでしょう。
竹田先生は、国内のホテルの部屋に聖書や仏典は置いてあるのに、なぜ古事記が置かれていないのか、と指摘されていますが、本当に不思議なことですよね。古事記や日本書紀は、日本の歴史、民族、あるいは文化の聖書のようなものなのに、その存在がすっかり忘れ去られているのは、どうしてなんでしょう。
『7つの習慣』も、よくビジネス・パーソンのバイブルといわれますが、ビジネス・パーソンのみならず、老若男女、国も世代も超えて、あらゆる人々に受け入れられているからこそ、そのように呼ばれているように思います。- 竹田
- 『7つの習慣』は全世界で3,000万部、国内だけでも160万部でしたっけ? そんなに出ているのは、今、西川さんもおっしゃったように、時間とか場所を問わず、普遍的なものだからだと思うんです。人間というのは、生まれや環境が違えば考え方も違ってくるのかもしれませんが、やっぱり普遍的で共通のものもある。イエス・キリストや仏陀も、そういう普遍的なことを教えているわけで、最終的には「幸せって何か」というところに行き着くように思います。
- 竹村
- では、古来の文化風土を有する日本の場合、どのようなものが普遍的なコアの部分になっているのでしょうか。
- 竹田
- 1人ひとりの国民の人格を尊重していくというのが、本来の日本の国の成り立ち、建国の精神といっていいと思います。今の日本国憲法でいえば、第13条「個人の尊重」と書かれている部分がそれに該当します。こういうものを読むと、国民1人ひとりを幸せにしていくことが国の目的だということがよくわかりますよ。
仁徳天皇も「国民のために天皇がいる。国民が不幸になったら、天皇の責任だ」ということをおっしゃっている。これは古事記ではなく日本書紀のほうに収録されている言葉ですが、こうした発想は、もともと神武天皇の「どこに都を置いたら平和に国を治められるだろうか」という問いから始まっています。
統治というと、支配とか管理的なイメージがありますが、統治を古事記の言葉でいうと「シラス(知らす)」になります。これは、天皇が存在するだけで国が束ねられる、もう少し具体的にいうと、天皇は祈りを通じて国を治めている、という意味です。つまり、天皇とは一言でいうと「祈る存在」であり、そうやって国民1人ひとりの幸せを祈り続けて、2000年以上経っているということになります。
 国を造ったのは神武天皇ですが、そのひいおじいさんにあたるニニギノミコトが地上に降りてくるとき、アマテラスオオミカミから「地上世界へシラセ」と命令されていて、そのアマテラスオオミカミもお父さんのイザナギノカミから「あなたは高天原をシラセ」という指令を受けています。
国を造ったのは神武天皇ですが、そのひいおじいさんにあたるニニギノミコトが地上に降りてくるとき、アマテラスオオミカミから「地上世界へシラセ」と命令されていて、そのアマテラスオオミカミもお父さんのイザナギノカミから「あなたは高天原をシラセ」という指令を受けています。
大日本帝国憲法の第1条も、最初の起草段階では、「大日本帝国ハ萬世一系ノ天皇コレヲシラスモノナリ」と書かれていたんですよ。でも、「シラス」という古い言葉ではわかりづらいということで、「統治」という言葉に置き換えられてしまったんです。なんで「知る」ことと「統治する」ことがつながるかというと、天皇が広く国の事情をお知りになるからです。事情がわからないと祈りようがない。元気にしているか、きちんとご飯を食べているか、国民の事情を国の隅々まで知っているからこそ、あの問題が早く回復したらいいとか、あそこに雨が降りますようにとか、祈れるわけで。天皇はわが子のように国民を愛し、その状態を知って祈り、その祈りを通じて国が束ねられていく。これが日本の統治なんです。
●7つの習慣は古事記とリンクしている?
- 西川
- それは「スメラギ」という言葉とも関係していますか。
- 竹田
- スメラギには「皇」の字が当てられていますが、スメラギスメラギコトというのは、国民の1人ひとりの存在を願い、祈る存在を指します。国家のために国民があり、国民は国王の私物であるというのは、前近代において世界中どこにでもあった考え方ですが、日本は太古の昔から、国民1人ひとりが、自由に、自分らしく、豊かに暮らせるにはどうしたらいいかということをずっと模索してきた国。個人個人が尊重され、自分らしく暮らせるというのが、2,000年前からの日本という国家のビジョンなんですよ。
- 竹村
 なるほど、勉強になります。
なるほど、勉強になります。- 西川
- 竹田先生のお話を伺っていると、竹村さんがいつもおっしゃっていることと、全部つながってくるような気がしますね。私自身、7つの習慣がなければ、とても生きてこられなかったと思うほどの影響を受けました。同じように、古事記や日本書紀に出会わなかったら、今の仕事を続けてこられなかったと思っているんです。
というのは、マーケティングとか、コンサルタントとかプロデューサーとか、そんな横文字の仕事をやっているうちに、途中でなんかあざといというか、なんでこんな人工的なことをやっているんだろうと思うようになったんです。新しすぎて、こんなものは日本の歴史や文化の中になかったんじゃないかと。
ところが古事記、日本書紀の中に、ヤゴコロオモイカネノカミという神様がいましてね、この人はアマテラスオオミカミが天の岩戸にお隠れになって世界が真っ暗になってしまったとき、アメノウズメノカミを踊らせて、その場にいた八百万の神々を爆笑させ、アマテラスオオミカミの気を引くことに成功した。つまり、古代のイベントプランナーでありプロデューサーなんですね。
古事記、日本書紀の中には、こういうありとあらゆる神様がいて、皆それぞれにさまざまな役割を担っている。『7つの習慣』を読んで「自分は何者なのか」ということをずっと考え続けていたところに、古事記、日本書紀を読んで、この部分に触れたとき、私自身、まさに自分の役割というものに気づかされ、自分の中で全部がつながった。ああ、いろいろなタイプの人がいていいんだな、日本というのはそういうものすべてを知っていただいている国なんだなと、本当に深いところから納得できたんです。私の勝手な解釈かもしれませんけれど(笑)。 - 竹田
- 『7つの習慣』を読んで、次に古事記を読むとバッチリということですね(笑)。